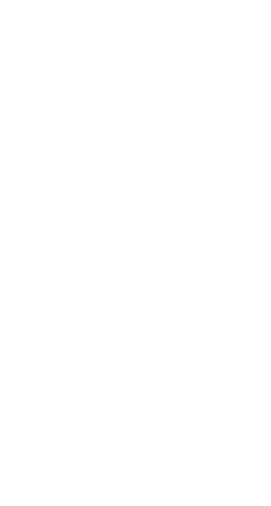ごまさば
No.328 / 2016年11月1日配信
関東から訪ねてきた友人はレシピ名の「ごまさば」をサバの魚種の「ゴマサバ」と勘違いしていたそうです。近年は博多で食べる「ごまさば」もグルメ番組などで多少は全国的に知られるようになりましたが、まだまだ浸透は不完全です。新鮮なサバの刺身をごまやわさび、醤油、みりんで和えた「ごまさば」はもっと自己主張すべきでしょう。
大阪や京都で生活した頃には、生サバは煮付けで、塩サバは焼いて、そして酢で締めたシメサバが食べ方の主流でした。鮮度を保てる流通機能が今ほど発達していなかったので、仕方ないのかもしれませんが、「サバを生(刺身)で食べる」習慣がほとんどなかったようです。鮮度が落ちるのが早いいわしやさばは水揚げされる地域しか楽しめなかったものかもしれません。
九州ではサバの漁獲量が全国で2位(2014年)の長崎県が控えています。「旬(とき)さば」というブランドで出荷している五島列島や対馬海峡で獲れたサバの味は私たちの舌を魅了します。大分にはその名も高き一本釣りの「関サバ」があります。ごまさば好きの私でも、さすがに「関サバ」にだけは、ごまをふりかける勇気はありませんが。
そんなサバも冬に向かって季節が進むほどに、脂がぐんぐん乗ってきて旨みも増してきます。大好きなサバを「ごまさば」に変身させ、伝承かめ壷造り・本格芋焼酎「幸蔵」で一杯やる楽しみは何物にも代えがたいものがあります。切り身の表面に残っている青い薄皮を眺めながら、一切れを口に運ぶと和えたごまの香りが幸せを運んでくれます。う?ん、最高です。