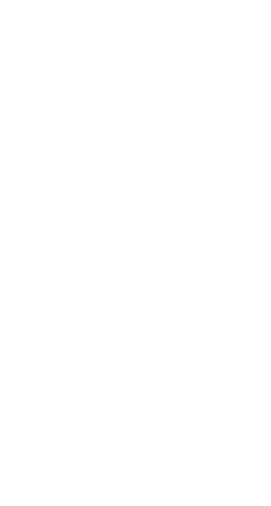桜の散り際
No.342 / 2017年3月21日配信
日本ほど四季を細やかに感じられる国は少ないといわれます。様々な顔を持つ美しい自然環境の中で、日本独自の繊細な感受性は長い時間をかけて育て上げられました。自然を克服するというより、同調できることに意味を見出した先人達の生き方を美しいと思います。今や、昔当たり前だった「情緒的」なことが「合理性」の中では新しいものに聞こえる時代になりました。
本棚の端に10年くらい前に読んだ藤原正彦氏の国家の品格(新潮新書)があったのでページをめくってみました。すると、しっかり忘れていましたが、日本人の桜に対する感性の鋭さを書かれたページがありました。桜の花が本当に綺麗なのは3、4日間だということですが、皮肉なことにそれを狙って春の嵐(風)がやってきては、きまって花びらを散らします。
たった数日に命をかけては潔く散っていく桜に無常の価値を見いだし、人生を投影していく日本人。武士道にもその散り際の美しさがみられます。一方で別の価値観を持つアメリカにおいても、ポトマック川沿いの桜まつりは人気で、本場日本をしのぐようなスケールに育っています。散り際に寄せる思いは違うでしょうが、まずは美しさに触れることが大切です。
昨年、20代から60代の半数以上が花見をしたと言われます。そしてその2/3が家族で出かけたというアンケートの結果も出ています。私も花見だけは家人と一緒でした。さあ、桜の季節。雨の満開にならないように、散り際が美しくありますようにと願いを込めて。今年も車はやめて、伝承かめ壷造り・本格芋焼酎「幸蔵」もスキットルに詰めて一緒に外出です。