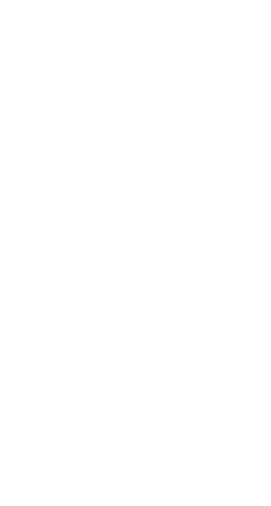鶏の水炊き
No.369 / 2017年12月11日配信
「夕やけや 唐紅の 初氷」。一茶の俳句にも出てくる「初氷」は冬の季語で、冬になって初めて張った氷のことです。初氷が張るこの時期、真っ赤な夕焼けが初冬の川面を照らします。冷たい川で染物屋が晒す反物も川面と一緒に、真っ赤に映える様をうたったものだとか。私が育った昭和時代も、つるべ落としの夕暮れは美しく、その赤い風景は今でも心に残っています。
風も出てきたようです。落ちかけの大きな夕陽は遊び疲れた子供たちの背中を赤く照らし、家族が待つ夕餉に足を急がせます。かじかんだ手をポケットに突っ込むと、ひび割れた手の甲が擦れてガサガサと音がします。引き戸を開けるといつものように「どこに行ってたの、あなたたち。遅いわよ、さあ、手を洗ってきなさい」と母の声が響きます。
そんな昭和の夕餉の思い出は鶏の水炊きです。骨つき鶏のぶつ切りと野菜が、アルマイト鍋の中で煮えています。鶏肉は好きでしたが、羽根を抜いた後のプツプツとした鶏の皮には抵抗がありました。もちろんそんなことくらいで、好き嫌いを言える家庭環境ではありません。それでも、父親の雷が落ちるまで、皮を避けようと兄と一緒に鍋の中をかき回したものでした。
博多の水炊きは白濁した鶏がらスープが特徴です。柚子ごしょうを効かせたポン酢につけていただきます。あの不得手だった鶏皮の部分も今では美味しく感じるようになりました。さあ、今夜も水炊きの出来上がりです。伝承かめ壷造り・本格芋焼酎「幸蔵」は昭和との相性も良いのか、すぐに水炊きの「あの時の鶏皮」の記憶が、懐かしく湯気の中に蘇ります。