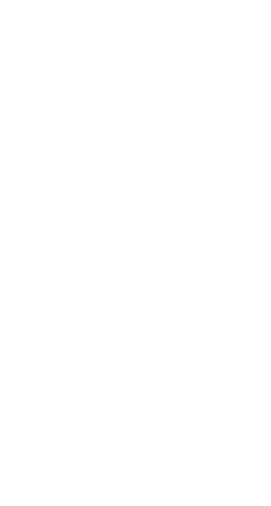赤いかき氷
No.391 / 2018年7月21日配信
ギラギラ太陽、白い入道雲。真っ黒に日焼けしているのに、友達よりも劣る黒さに悔しがってた小学生の夏。市民プールの帰り道、急にアブラゼミの声がしなくなったと思ったら、暗くなった空から大粒の雨が激しく降って来ました。私と友達は雨をやり過ごそうと民家の軒下に避難しました。思いのほか雨は降り続き、小降りになることがありません。
そんな私の目に数軒先のお好み焼きの看板が目に入ります。冬に食べたことはありましたが、小麦粉を溶き、もやしと天かすを挟んで焼き上げただけのものです。それでも、さっぱりとしたウスターソース味が美味しかったことが思い出されます。しかし、それ以上に気になるのがその横で「氷」と布に大きく染められた一文字。そんな私を友だちはじっと横目で見ていました。
「氷、食べていこうか」と友だちは口を開きました。もちろん私のポケットにはそんな小遣いなど入っていません。力なく首を横に振る私を見て、お金は僕が払うからと裕福な友だちは誘います。「理由もなく他人から施しを受けてはいけません」と、母の言葉が聞こえて来ますが、私は待てと言う命令を無視した犬のように、しっかり欲望に負けてしまいました。
帰宅すると「かき氷食べて来たでしょ」と母からすぐに見破られました。「口の中が真っ赤じゃないの、どうしたのそのお金」と問い詰められたのです。「そのかき氷代、友達に返して来なさい」とタンスから出してきたお金を手渡されました。伝承かめ壷造り・本格芋焼酎「幸蔵」が入っているグラスの中で、氷が笑っています。真っ赤なウソはすぐに見破られます、と。