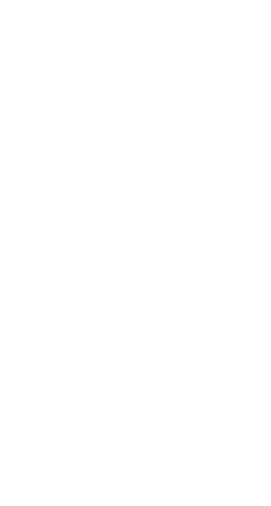処 暑
No.393 / 2018年8月11日配信
旧盆でご先祖様を送るころには、暑かった夏も朝夕には涼しさを感じるようになっていたものです。しかし、しかし、地球温暖化現象が叫ばれて以来、お盆が過ぎても夏は続き、今年も酷暑だなあと、うんざりしてしまうのが近年通例となりました。当然ではありますが、8月初旬の「立秋」とは名ばかりで、猛暑に最中に涼感など望むべくもありません。
それでは「立秋」の次の二十四節季である「処暑(今年は8月23日)」はどうでしょうか。江戸時代に出版された暦の解説書「暦便覧」によると、処暑の時期は、暑さも峠を越し、和らぎ始める時期のようです。それも昔の話。昨年の8月23日の最高気温は35.8度(福岡)を記録し、その後の2日間は36度を超える暑さでしたし、もちろん熱帯夜でした。
「夏休みの宿題ちゃんとやってる?毎日の気温は書き留めておかないと、後で困るでしょ」と、夏休みも中盤を過ぎると必ず母から注意を受けていました。遊びに懸命だったせいで、夏休みの友(メインの宿題帳)は遅れ遅れになっています。そして自由研究の工作を含めた最後の追い込み(苦しい、苦しい)が、必ず夏休みの終わりにやってきました。
9月も間近になると、宿題や提出物ができていない生徒にとってはもう地獄の様な日々となります。母の言うことを真面目に聞いておけば良かったと大後悔。夏休みの友の気温を書き込む欄など余白ばかりです。処暑、伝承かめ壷造り・本格芋焼酎「幸蔵」のロックグラスを手にしながら、思い出せば今だに冷や汗。気温を毎日記録することさえも大変に思えた少年時代でした。