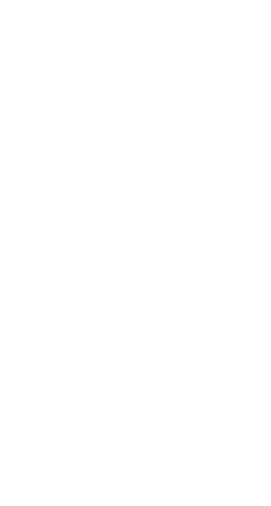縁起物
No.514 / 2021年12月21日配信
今よりもっと気温が低かった冬、時には手が切れるような冷たい水を使いながら、正月を控えた母はおせち料理を作っていました。その手は赤く晴れています。「まだお祖母さんが生きていたときは、井戸水だったから案外温かだったけどね」と水道の蛇口を捻っていました。九州でも、たまには凍りつく寒い夜もあり、むき出しになっていた水道管に藁縄を巻いていた父のことを思い出します。
母は水で洗った黒豆を強火や弱火でしっかりと時間をかけて煮込んでいました。その他にも田作り、がめ煮(筑前煮)、数の子、昆布巻きとおせち作りに忙しくしていました。紀文の調査では今でもおせち料理を正月に食べている人は約50%だそうですが、はたして手作り黒豆を作っている人はどのくらいいるのでしょうか。昭和の昔とは違った結果になるのは目に見えていますが
元旦の朝、質素だけれど、普段は食べることのないおせち料理が食卓に並んでいます。家族が顔をそろえて正座します。子供ながらその厳かな雰囲気が大好きで、「何か特別な感じ」を結構楽しんでいました。そして何よりワクワクできたのは、子供でもお酒(お屠蘇)に触れることができることができる日だったからかもしれません。私はその当時からそちらの資質だけは十分だったわけです。
「黒豆は元気にまめに働けるようにように、昆布は喜ぶ、数の子は子宝・子孫繁栄、雑煮のお餅は神様に捧げる神聖な食べ物で、正月のお祝いに欠かせないものよ」と母は私たち兄弟に「縁起の良い」おせち料理の意味を話して聞かせました。年の瀬を迎えると、そんな母の声を思い出します。来年はいい年になるようにと、幸せの縁起物・伝承かめ壷造り・本格芋焼酎「幸蔵」にも願いをこめて。