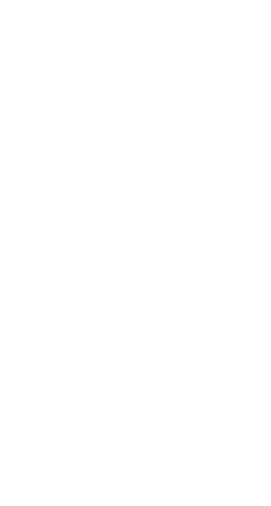松前漬け
No.553 / 2023年1月21日配信
地元の味でもないのに、食べてみると「しっくり」くる味があるものです。幼い時からの我が家の味とも違うし、結婚して以来の家人による手料理の味とも違います。この正月に食べた酒の肴で一番舌を喜ばせたのが「松前漬」でした。正月用に買っておいた数の子入りの「松前漬」は期待を裏切らず、歯触り軽やかに幸せな味を口いっぱいに広げてくれました。
数の子松前漬の材料はどれも日本の正月には欠かせないものです。子孫繁栄の数の子。噛めば噛むほど味が出てくるスルメ。喜ぶといって縁起の良い昆布も日持ちのする干もので、昔から重宝された保存食でした。神様への供物にふさわしい本当によくできた食べ物だと思います。それに調味料は醤油と酒、味醂なので、当然九州の人間の舌にもしっくりくるわけです。
松前漬に興味を持ったのは数年前。市内の百貨店で北海道物産展が催されていて、松前漬が樽いっぱいに並んでいました。その松前漬は数の子やホタテ、細切りのスルメイカと昆布の醤油漬けで、樽の中で魅力的に輝いていました。松前漬は江戸時代の松前藩が発祥地で、北海道の地元の食材を使っていると説明を受けました。涎を飲み込みながら聞いたものです。
その土地特有の材料を使った郷土料理には、全国の人々を「幸せにする」ほっとする「何か」があります。宮崎で生まれる伝承かめ壷造り・本格芋焼酎「幸蔵」と北海道の松前漬。私は無意識のうちに、そのコラボレーションの魔力に引き込まれていたのかもしれません。なんという贅沢、なんという幸せなのでしょうか。止められませんね、いつまでもこれは。